
ニやカワゲラ、トビケラ、ヒラタカゲロウ、ヘビトンボなどもいました。カワニナもすごくたくさんいます。 乙女川ではカワゲラ、トビケラ、ヒラタカゲロウ、ヘビトンボなどの「きれいな水」にすんでいる生き物が多くいました。 ここでもヒラタドロムシが石にへばりついていました。石のうちについている小さな卵をいっぱいみつけました。小さなコガネムシみたいな虫が卵の近くにいたので何かなとふしぎに思い、本で調べたら「ヒラタドロムシの成虫」と書いてあり、びっくりしました。 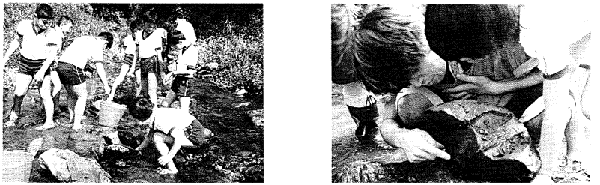
調査の結果、次のようなことが分かりました。大雨河の川はだいたいが「きれいな水」にすむ生き物が多くいるので、「きれいな川」が多い。中でも、河原の川の上流にはアマゴもいて、水もつめたく一番きれい。 雨山の川は、コンクリート工事のせいか「すこしきれいな水」になっている所もある。大代の川には、川の虫がすみにくい「きたない水」になっている所があった。よごれのもとが工業用地のため池からきているみたいだがどうしてかなあと思った。こうした結果から、10月7日に、再度、大代の川のよごれを調べてみようと4・5・6年全員で調査活動をしてみました。 夏休みの時と比べると雨のふった後ということもあり、川の水がすんでいました。川の石をひっくり返すと、ヘビトンボ、トビケラがいたし、サワガニ、ヤゴなどもいました。少し水がきれいになったのかなと思いました。 同じ日に、河原の学校川で同じ調査をして、大代の川と比べてみました。水温が20度と17度で、河原川の方が3度も低く冷たかったです。 大代の川にも川の生き物がいたけれども、河原川では、その種類も数もものすごく多く川の生き物が豊富なことが分かりました。 両方の川の石を比べると大代の川の石はずいぶん黒ずんでいることが分かりました。きれいな川には、やっぱりたくさんの生き物がすんでいます。川に入っても気持ちがいいです。 家の人に聞くと、「昔はどの川も今の河原川よりももっともっときれいな川だったんだよ。」と話してくれました。 わたしたちのふるさと大雨河の川が魚たちが喜ぶきれいな川になってほしい!大好きな川でうんと遊びたい!だから、みんなでどうしたらきれいな川になるか、「子ども環境サミット」の発表までに考えてみることにしました。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|